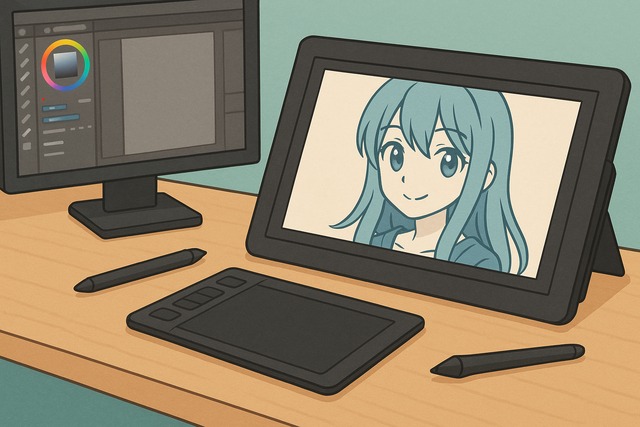影は形を説明し、光を信じさせる重要な要素です。けれども描いている最中は情報が多く、どこを暗くどこを残すかで迷いが生まれます。そこで本稿では、三値の幅を先に決める方法、エッジの硬軟差で主役を立たせる考え方、反射光と接地影の扱いを一貫した手順に落とし込み、練習と本番の双方で再現できる影の設計を示します。
まずは短時間で回せるルールを整え、次に質感や構図に応じて調整し、最後に仕上げで整合させる流れを身につけましょう。
- 紙は中目A4、鉛筆はH・HB・Bの3本に限定
- 光源は一灯で固定し影の方向を統一
- 三値を3分で仮置きし最大差を固定
- 接地影は主役付近だけ硬く他は緩やかに
- 反射光は暗部に細く残し塗り潰さない
影の基礎と三値の関係
影を描く前に、白・中・黒の三値を仮決めしておくと判断が一気に軽くなります。最暗部の帯と最明部の幅を先に固定し、中間を広げるのか狭めるのかで質感を選び分けます。ここでは影の部位名と役割を表で整理し、どこを硬くどこを柔らかくするかの目安を明確にします。
| 部位 | 役割 | 目安 | 描き方の要点 |
|---|---|---|---|
| 固有陰影 | 形の向きの説明 | 面に沿う | HBで面として置きHで整える |
| 接地影 | 浮きを止める | 主役付近が最硬 | Bで縁を締め遠方へ柔らかく |
| 反射光 | 空気を通す | 暗部の10〜20% | 練りゴムで細く起こし縁を締める |
| 半影 | 移行の帯 | 長さで質感変化 | 線を帯で重ね段階を作る |
| 縁のエッジ | 主役の強調 | 硬軟差で誘導 | 主役だけ一段硬く他を抑える |
注意: 「黒さ」でなく「幅」を管理します。同じ濃さでも最明と最暗の幅の取り方で金属にも布にも見えます。幅は最初に決め、仕上げで濃度を微調整すると迷いが減ります。
ステップ1: 片目で最大コントラストの対を探し、白・中・黒を3分で仮置き。
ステップ2: HBで半影の帯を直線ステップで刻み、面の向きを先に説明。
ステップ3: Bで接地影の主役側だけ縁を締め、奥は柔らかく逃がす。
ステップ4: Hで最明部のノイズを整え、塗らない白を守る。
ステップ5: 反射光を細く起こし、暗部の中で呼吸させる。
接地影と固有陰影を見分ける
接地影はモチーフの外側に落ちる影、固有陰影はモチーフ自体の暗い面です。床の面に沿う接地影は距離で柔らかくなり、固有陰影は形の傾きで帯の幅が変わります。観察ではまず影の輪郭を線で取らず、面として見ます。縁をいきなり硬くせず、主役付近のみを最後に締め、手前から奥への空気の流れを途切れさせないことが要点です。
三値の幅を先に決める
最明は紙の白を残し、最暗はBで面づけ、中間はHBの二段で管理します。幅を先に固定すれば細部の情報が増えても迷いません。特に金属やガラスでは最明の幅を細く取ると質感が立ち、布では中間の幅を広げると柔らかく見えます。幅は濃さより先に決める指標で、仕上げ時の濃度調整の基準にもなります。
エッジの硬さで主役を立てる
主役の縁だけを硬くし、二番手や背景は一段柔らかくします。硬軟差は視線誘導の装置で、全てを硬くすると画面が平板になります。硬さは接地影の手前側で最大化し、遠ざかるにつれて緩やかに移行させます。局所の硬さではなく、距離で変化する緩急を設計することで、奥行きが自然に立ち上がります。
反射光の扱いをルール化
暗部の中の細い明るさは、形の裏側から回り込む光です。反射光を広げ過ぎると物体が軽く見えるため、幅を暗部の10〜20%に抑えます。位置だけ先に印を付け、仕上げで練りゴムで起こしてBで縁を締めるのが安全です。反射光は「塗らない白」ではなく「暗部の中の明るさ」である点を意識します。
光源の位置と影の形
光が高いほど接地影は短く濃く、低いほど長く薄くなります。光が正面寄りだとハイライトが広がり、側面寄りだと帯が細く鋭くなります。観察では光源の方向を一度だけ指差し確認し、影の伸びる方向を面に沿ってイメージします。影の形を「投影図」として捉えると、床面や壁面のパースとも自然に整合します。
影は三値・エッジ・幅という三つのハンドルで管理します。まず幅を決め、次に硬軟で主役を立て、最後に反射光で空気を通す。順序を固定すれば、情報が増えても迷わずに立体感を維持できます。
デッサンの影を決める時間配分と手順
短時間で安定した影を作るには、時間を区切り役割を分けるのが近道です。ここでは30〜40分のワンセッションを想定し、三値の仮置き・半影の設計・仕上げの整合に配分します。時間が限られるほど優先順位が明確になり、重要な影だけが画面に残ります。
メリット方式: 先に三値→半影→接地影→反射光。比較の基準が明確で再現性が高い。
デメリット方式: 細部から入る。偶然の当たりは出るが全体整合が崩れやすい。
Q: 途中で時間切れならどうしますか。A: 三値で止めて終了します。次回は半影から再開し、比較可能な状態を保ちます。
Q: 影が重くなりがちです。A: 反射光の幅を先に印し、暗部の中に細い帯を必ず残します。
Q: 消しゴムで明部を作って良いですか。A: 最後に限定的に。塗らない白を主力にし、起こしはアクセントです。
コラム: 古典石膏像の講座では、半影の設計に多くの時間を割きます。明暗の境目を帯で扱う伝統は、現代の短時間デッサンにも有効です。帯の密度と長さで質感を語る意識が、濃度主義からの脱出を助けます。
配分のモデルを作る
10分で三値、20分で半影と接地影、5分で仕上げという配分をひとまず固定します。毎回の終了時に「次回やること」を一行で書くと、練習の立ち上がりが速くなります。時間を配る行為自体が編集であり、影の情報の優先順位を明確にしてくれます。配分は守るほど比較が効きます。
仕上げの整合点を決めておく
最終的に見る場所を先に決めます。例えば「主役の縁の硬さ」「接地影の濃さ」「反射光の幅」など三点に絞り、そこだけは毎回到達します。整合点があると、時間切れでも完成の手応えが残り、次の一枚へスムーズに移行できます。到達しやすい整合点を選ぶことが継続の鍵です。
情報の遮断と選別
背景の模様や反射の細部は、初期段階では意図的に見ないようにします。主役の形と影の幅が決まるまで、余計な情報を遮断します。選別の目を鍛えるほど、影の要点が濁らず、短時間でも説得力を保てます。見ない勇気は編集の力です。
時間配分を固定し、整合点を三つに絞るだけで、デッサンの影は安定します。見ない情報を決めることも設計の一部であり、短時間でも再現性の高い一枚に近づきます。
形とパースが影に与える影響
影は形の投影であり、形やパースの誤差は影に敏感に現れます。直線ステップで輪郭をまとめ、中心線と対角線で傾きを検証すれば、影の伸びや角の位置が自然に整います。ここでは形→影の順で詰めるための確認手順を具体化します。
- サイティングで縦横比を仮決めし、外形を直線で構成する。
- 中心線と対角線で傾きのズレを検査する。
- 接地面のパースを先に決め、影の方向を面に沿わせる。
- 角の位置を点で押さえ、面として影を落とす。
- 遠方ほどエッジを柔らかく、手前は硬く管理する。
- 主役の通り道に余白を確保し、影の重心を置く。
- 最後に反射光と半影の長さで質感を整える。
直線ステップは曲線を段階化し、誤差の原因を可視化します。影の形は面に依存するため、面の向きが合えば自然と影の伸びも整います。曲線を早く追わず、直線でまとめる忍耐が結果的に時間短縮になります。
失敗1: 床パースを後回し→影が浮く。先に床の消失点を意識して接地影を面で置く。
失敗2: 輪郭の曲線を早く追う→比率が甘くなる。直線で段階化し最後に丸める。
失敗3: 主役と影の重心が離れる→目が迷う。主役近くのエッジだけ硬くして誘導。
用語: サイティング=鉛筆で比率を測る行為。
用語: 直線ステップ=曲線を直線の階段で詰める方法。
用語: 消失点=パース線が収束する仮想点。
用語: カウンターシェイプ=外形の外側にできる空白の形。
用語: 半影=明暗の移行帯で質感を語る部分。
接地面パースを先に決める理由
接地影は床の面に沿って伸びます。床の消失点が曖昧だと、影は物体から離れて見え、浮いた印象になります。外形より先に床の軸を引き、影の方向を決めてから面として落とすと、接地の説得力が格段に上がります。床が決まれば、モチーフの傾きも自然に収まります。
角の位置と影の転換点
箱や円柱の角は、影の形が折れたり伸びたりする転換点です。点を先に押さえ、帯でつなぐと、影の形が論理的に構築できます。曲線で繋ぐ前に直線で検討することで、誤差が早い段階で見つかり修正も容易です。転換点の設計が影の説得力の土台になります。
余白と重心の設計
主役の近くに影の重心を寄せると、視線が迷わずに入ります。余白は呼吸であり、情報を減らすための装置でもあります。影で画面が黒く重くなりがちなときは、二番手のコントラストを一段抑え、主役周りに空白を意識的に作ります。重心の設計が画面の落ち着きを作ります。
形とパースを先に整えれば、影は自然に従います。床の軸→転換点→帯で構築する順番で、余白と重心を設計すれば、影の説得力と画面の安定が同時に得られます。
質感別の影の作り方
質感は三値の幅と半影の長さ、それにエッジの硬軟で説明できます。ここでは布・金属・木・ガラスを例に、幅の管理と方向の一貫性で影を組み立てる手順を示します。ぼかしに頼らず、線と面で質感を立ち上げます。
- 布: 中間調を広く保ち、折り目の頂点で硬く谷は柔らかく移行
- 金属: 最明の帯を細く鋭く、縁の最暗をBで締める
- 木: 年輪方向にハッチを流し、節周辺で密度と硬さを上げる
- ガラス: 背景の明暗を借り、最明は塗らない白で抜く
- 紙: 半影を長めに、表面の粒で中間を支える
- 陶器: 最明は広め、接地影にわずかに反射を残す
- 革: 中間の幅を保ち、艶の帯は細く途切れさせない
数分で判断を確定するには、数値の目安が役立ちます。金属の最明幅は全幅の5〜10%、布の反射光は暗部の10〜20%、木の節周囲の硬さは通常より一段硬く、ガラスは背景との対比で最明を守る、などの基準を持つと、迷いが減ります。
□ 最明の帯を数本の線で囲い、幅を先に決める。
□ 暗部は面として落とし、途中で途切れさせない。
□ 反射光は位置だけ先に印し、最後に細く起こす。
□ 接地影は主役付近だけ硬く、距離で柔らかく。
□ 質感の違いは半影の長さで表現する。
布の半影と折り目
布では半影が主役です。頂点の近くで硬さを出し、谷は時間をかけて移行させます。中間調を広く保つため、最暗と最明を細く管理し、幅の対比で柔らかさを作ります。折り目の方向に沿ってハッチを流すと、面の向きが崩れず安定します。ぼかしは最後に必要な分だけ使い、均一化を避けます。
金属の帯と反射
金属は最明と最暗の幅が近づくほど鋭く見えます。帯の左右で明暗を急激に切り替え、縁の最暗をBで締めます。映り込みは必要最小限に絞り、画面の中心に関係する情報だけを残します。反射光は暗部の中に細く保ち、過度に明るくしないことで重量感が失われません。
木とガラスの違いを方向で作る
木は年輪の方向にハッチを流し、節付近で硬さと密度を上げます。ガラスは物体そのものより背景の明暗を借り、最明は塗らない白で抜きます。どちらも方向と幅のルールを先に決めることで、短時間でも質感の差が立ち上がります。線と面の役割分担を意識します。
質感は「幅」と「方向」で決まります。布は中間を広く、金属は帯を細く、木は方向を通し、ガラスは周囲を借りる。ルールを先に選べば、手数を増やさず説得力が上がります。
観察と簡易計測で影を外さない
影の位置と濃さは感覚に任せず、観察の手順と簡易計測で決めます。片目固定・アタリの点・幅の印の三点で、迷いやすい反射光と接地影の関係を安定させます。小さな道具立てが、影の確度を高めます。
・最明の幅は紙の白で守る(5〜10%)。
・反射光の幅は暗部の10〜20%に制限。
・接地影の硬さは主役付近最大、奥へ段階的に緩和。
ケース: 球体の暗部を塗り潰して軽く見えた。反射光の細い帯を起こし、接地影の縁だけ硬くしたところ、浮きが止まり立体感が回復した。幅と硬さの基準を先に作るだけで迷いが減った。
注意: 目が慣れるほど暗部は暗く感じます。途中で紙から目を離して距離を取り、相対で見直します。比較の相手を作ることで、暗さの過剰を抑えられます。
片目とアタリの点
片目で最大コントラストの位置を探し、アタリを点で置きます。点は線より情報が少ないため、誤差の蓄積を防ぎます。点を帯で結ぶときに初めて線が現れ、影が面として立ち上がります。最初から線で輪郭を囲うより、点の連結で作る方が柔軟です。
幅の印を先に置く
最明と最暗、それぞれの幅の端に軽い印を置きます。幅が決まれば濃度は後からでも追いつきます。印は消しても痕が残らない薄さで、位置だけを決めるつもりで入れます。幅という物差しを持つだけで、影の判断は一段階単純化します。
休止と距離のリセット
数分ごとに視点を画面から40〜60cm離し、全体のグラデーションを確認します。局所の暗さが全体の設計を壊していないか、接地影の硬さが主役だけに集中しているかをチェックします。休止は判断のノイズを掃除する時間です。
観察は手順です。片目→点→幅の印→距離のリセットで、影の過剰や不足を避けられます。数値の目安を持つと、練習と本番の差が小さくなります。
仕上げで影を締める評価と改善
仕上げの目的は整合です。コントラストとエッジ、反射光と接地影の関係を最終点検し、主役の周囲だけに力を集中させます。評価の翻訳と一行課題を習慣化すれば、次の一枚への移行が速くなります。
- 三値の差が初期設計どおりかを全体で確認。
- 主役の縁だけ一段硬く、二番手は抑える。
- 接地影の硬さが距離で緩んでいるか点検。
- 反射光の幅が暗部の中で細く保たれているか。
- 最明は塗らない白で守られているか。
- 所要時間と次の一行課題を記録。
- 3分離れて全体の呼吸を確認。
メリット: 整合点を固定すると比較が容易で上達が見える。
デメリット: 固定し過ぎると遊びが減る。月に一度は自由制作で感覚を開放。
ステップ1: 3分俯瞰で主役周りの硬さを決め直す。
ステップ2: 線端のガタつきをHBでならす。
ステップ3: 反射光の縁をBで締め、帯を細く保つ。
ステップ4: 二番手のコントラストを10〜20%抑える。
ステップ5: 一行課題を記録して終了。
講評を作業に翻訳する
「暗い」→「反射光を細く起こす」「重い」→「二番手のコントラストを一段下げる」「甘い」→「接地影の縁を主役側だけ硬くする」。抽象語を作業動詞に変換すると、次の一枚の立ち上がりが速くなります。紙の裏にテンプレートを印刷しておくと便利です。
短時間仕上げの訓練
5分だけ仕上げ時間を設け、主役の縁と接地影に限定して調整します。制限時間が重要度の低い情報を自動的に削ぎ、画面の集中が増します。完成を急がず整合を優先する姿勢が、練習と本番の差を縮めます。
継続を支える記録とご褒美
「一週間で7枚、整合点3項目達成」などの指標を決め、達成したら小さなご褒美を用意します。記録は上達の地図であり、楽しさは継続の燃料です。習慣化の仕組みを先に作ると、影の精度は自然に上がります。
仕上げは整合、講評は翻訳、次回は一行。工程を短く回し、主役の周囲だけを確実に締める習慣が、安定した影を生みます。
まとめ: 影は三値・エッジ・幅という三つのハンドルで管理し、接地影と反射光の関係を時間配分の中で整えます。
形とパースを先に整えてから幅を決め、質感に応じて半影の長さを調整し、仕上げで主役周りだけを一段硬く締める。観察と簡易計測の手順、数値の目安、講評の翻訳を習慣化すれば、短時間でも立体感は揺らぎません。今日の一枚に三つの整合点を置き、次の一枚へ迷いなく進みましょう。