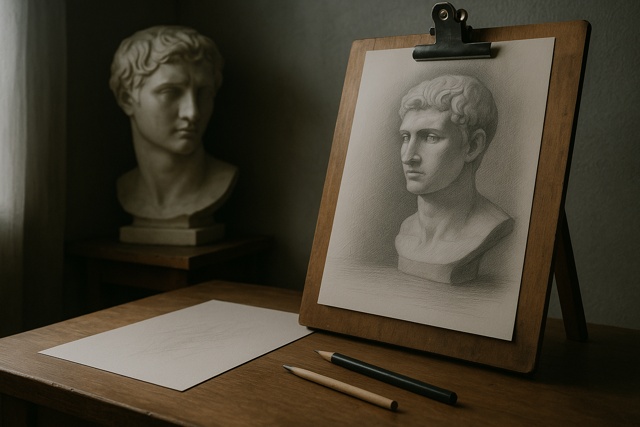鉛筆で影を付けるときは、光の位置を決め、面を簡略化し、明暗差を段階的に積み上げます。道具は少なくても、順序と観察が整えば形は自然に浮かびます。
本稿では、光質と距離、境界の硬さ、反射光の捉え方を中心に、練習の流れとチェックの基準を具体化します。仕上げの粒状感や紙の選び方まで触れ、再現性のある手順にまとめます。
- 光源は一つに固定し影の方向を統一します。
- 形を面で捉え三値から始めて段階を増やします。
- 硬い境界と柔らかい境界を描き分けます。
- 反射光は控えめに置き自然な量感を守ります。
- 筆圧を分割し紙目との摩擦を活かします。
- 番手はHB中心から必要に応じて拡張します。
- 仕上げは練り消しで光を拾い整えます。
絵の影の付け方を鉛筆で学ぶ基本
最初の山場は観察と手順の整合です。光源の位置と距離を決め、形を面に単純化し、三値で当ててから階調を増やします。硬い影と柔らかい影の差を早期に定義すると、後の修正が少なくなります。
光源の位置と距離の決め方
光源は一つに限定し、用紙の外に想定図を小さく描きます。高さと左右のオフセットを具体化すると影の方向が迷いません。距離が近いほど影は濃く境界は硬くなります。遠い光や拡散光では全体が穏やかに回り、半影が広がります。机上灯なら斜め上四十五度を基準にし、毎回同じ位置で固定します。
最初は立方体と球体で検証します。側面に入る光の角度を意識し、投影の向きと長さを合わせます。模型を紙の近くに置くと投影は短く濃くなり、離すと長く薄くなります。観察のたびに小スケッチで比較すると差が把握できます。
形を面に分けて明暗を置く
細部より面のまとまりを優先します。三値法なら「光」「中間」「影」の三段で配置し、最初は均一な面で塗ります。球はハイライト帯を残し、反対側に核心影を置きます。立方体では手前面と側面の明度差をはっきり分け、天面の明るさで光の高さを示します。面の境界は形の情報なので、線より面の幅で伝えると安定します。
- 輪郭は薄いHBで構造線として置きます。
- 三値をフラットに塗り分けます。
- 半影と反射光の帯を必要最小限に足します。
- 核心影の濃度を一点だけ最も深くします。
- 調子の段差をなだらかに接続します。
- 輪郭線を調子に吸収し線感を減らします。
- ハイライトを練り消しで拾って締めます。
- 投影のエッジを床面の材質で変えます。
影の三要素を見極める
影は「核心影」「半影」「反射光」で構成されます。核心影は最も光が届かない帯で、点ではなく面として置きます。半影は明暗の遷移領域で、用紙の白が透ける程度に重ねます。反射光は床や隣接物からの跳ね返りで、置きすぎると形が膨張します。核心影のごく一部に最暗部を作ると、全体が締まり奥行きが増します。
エッジの硬さをコントロール
境界の硬さは材質と距離を説明します。金属やガラスは硬め、布や皮膚は柔らかめに設定します。距離が離れると空気の散乱で境界は緩みます。輪郭を黒線で回すと記号化するので、調子の差で境界を成立させます。硬いエッジは短いストロークで重ね、柔らかいエッジは往復のストロークを重ねてグラデーションを作ります。
明度階調と鉛筆の番手切替
HBを基軸に、2Bと4Bで深度を追加します。紙が滑る場合はB系を増やし、紙目が強い場合はHBで層を作ってからBで締めます。段階は五〜七段を目安に増やすと破綻しません。最暗部だけ6Bを少量使うと締まりが出ます。番手変更時は一段上げたら一段戻して馴染ませると、段差が出ずに滑らかです。
- ミニFAQ:光源は毎回同じでよいですか
- 基礎練習は固定が有利です。変化を学ぶ段階で位置をずらします。
- 練り消しとプラスチック消しの使い分けは
- 広い面の持ち上げは練り消し、鋭い抜きは樹脂消しを角で使います。
- ブレンダーは必要ですか
- 必須ではありません。紙目を活かす場合は使わず、金属などで用います。
光の設定と三値の置き方、境界と番手の切替が基礎の核です。最暗部の一点を決めて全体を相対で合わせると、迷いが減り再現性が高まります。
価値を設計する明暗マップと観察の優先順位
明暗は形を説明する言語です。初手で全体の幅を決め、面ごとの相対を配分すれば、細部は後から整えられます。観察の優先は「光の方向」「面の向き」「材質の反応」の順が安定します。
三値から五値へ段階を増やす手順
三値でまとまりを作った後、最も暗い面を二段階に分けます。次に中間域を二分し、明部のハイライト帯を残します。段階を増やすたびに最暗部を基準に再評価します。濃度の追加は面の中心から始め、境界に寄せてなじませます。広い面は円運動のストロークでムラを減らします。
メリット:段階的に増やすと破綻が少なく、修正が容易です。全体の統一感が保てます。
デメリット:序盤は地味で時間がかかります。速さを求めると粗さが残ります。
観察の順番で迷いを減らす
最初に光源を確認し、面の向きを矢印で書き込みます。次に材質の特徴を一語でメモします。金属は光沢、布は繊維、木は木目などです。最後に周囲の反射要因を絞り、反射光の寄与を推定します。順番を固定すると判断が一定になり、毎回の差が小さくなります。
大きな影から先に固める理由
小さな影は大きな影の子どもです。親の濃度と方向が決まれば、子の調整は短時間で済みます。投影の落ち先を先に確定し、核心影の位置を決めると、細部の影が自動的に整列します。筆圧管理が安定し、消しゴムの介入も最小化できます。
コラム:古典デッサンでは、明暗の幅を「価値」と呼びます。価値が決まれば、形は自ずと読めるという考え方が骨格になっています。現代でも通用する普遍的な視点です。
明暗の段階追加と観察の順序固定で、判断が簡素になります。大きな影を親として先に固めると、全体の整合が取りやすくなります。
境界の設計とストロークの方向性
境界は形と材質を同時に語ります。硬さの設計とストロークの方向が一致すると、紙目のノイズが整理され密度が上がります。輪郭線の代わりに調子差で輪郭を成立させます。
硬い境界の作り方
短いストロークで積層し、最後にエッジの手前側を一段暗くします。外側を薄く抑えると、内側が硬く見えます。金属やプラスチックでは、境界沿いに狭いハイライト帯を残し、反対側の核心影を強調します。筆圧は瞬間的に高くし、持続圧は軽く保ちます。
柔らかい境界の作り方
往復ストロークで帯を広げ、中心を薄く両端を濃くする「山形」配置を基本にします。肌や布では、境界帯を広く取り、最暗部を狭く短くします。必要ならティッシュで一回だけ軽くならし、紙目を潰しすぎないようにします。境界の外側に薄い反射光を残すと、柔らかさが増します。
ストロークの方向と形の整合
面の大きさや曲率に沿って方向を決めます。円筒は輪切り方向、球は子午線と緯線を意識した短い弧で重ねます。木材は木目方向を基準にし、金属は長手方向に滑らせます。交差ハッチは角度差を小さくし、二層までに留めるとクリアに見えます。
- チェック:境界帯の幅は材質で説明できるか。
- チェック:ストロークは面の流れに沿っているか。
- チェック:最暗部は一点に限定できているか。
- チェック:反射光は主張しすぎていないか。
- チェック:輪郭線が残っていないか。
事例:金属スプーンは縁を硬く、柄の円筒部は帯を狭く設定。皿面の反射を最小限に抑え、最暗部をボウル内に一点作ると金属感が立ちます。
硬さの差と方向の一致が、形の説得力を決めます。帯の幅を言語化してから手を動かすと、再現性が上がります。
反射光と環境光で量感を調整する
反射光は形を起こす補助ですが、過剰にすると膨らみます。環境光とのバランスを取り、核心影を失わない範囲で明度を持ち上げます。床や隣接物の色も影響します。
反射光の置き方
反射光は核心影の外側に細い帯として置きます。明るさは中間調の下限程度が目安です。床が明るいと反射が強くなりますが、最暗部を壊さないように幅を抑えます。金属では反射が強く帯も硬め、布では広く柔らかくなります。置いた後は境界を一往復で接続して馴染ませます。
環境光の管理
部屋全体の明るさが高いと、影のコントラストが下がります。練習では光を一点に絞り、周囲を落として差を確保します。窓光は時間で変化するため、短時間で区切って描きます。環境光が強いときは、全体を半段暗く寄せて相対差を維持します。
彩度の錯覚と鉛筆の役割
鉛筆は無彩色ですが、周囲の彩度に影響されて明度の見えが変わります。カラフルな下地や物が周囲にあると、影が薄く見える錯覚が起きます。練習ではグレーの下敷きを使い、視覚の基準を安定させます。下敷きのグレーは中間域の評価に役立ちます。
- 基準:反射光は中間調下限で抑える。
- 基準:最暗部は一点だけ最下限に置く。
- 基準:環境光が強いときは全体を半段寄せる。
- 基準:窓光は時間を区切り短時間でまとめる。
- 基準:下敷きグレーで目をリセットする。
ミニFAQ:反射光が強くて膨らみます。どうしますか。答えは最暗部を先に作り、反射光帯の幅を半分に削ります。床の明度が原因なら、床面を一段落として相対差を戻します。
反射光は量感の微調整です。最暗部と帯の幅の管理で、膨らみを防ぎながら形を起こせます。
紙と鉛筆の相性と筆圧コントロール
紙目と芯の硬さが噛み合うと、少ない層でも密度が出ます。筆圧は持続圧と瞬間圧に分けて管理し、層の重ね順で粒状感を整えます。道具の相性を把握すると安定します。
紙の選び方と層の設計
細目は均一な面作りに、中目は質感兼用に向きます。荒目は粒状感が立ちます。HBで地を作り、B系で締め、最終層は方向を変えて薄くかけます。紙目が強い場合は、斜めにストロークを交差させると穴が埋まります。擦筆は最終手段として使い、紙目を潰しすぎないようにします。
筆圧の分解と再構成
持続圧は軽く長く、瞬間圧は短く鋭く。面のベースは持続圧で敷き、最暗部や硬い境界は瞬間圧で重ねます。握りは鉛筆を後ろ持ちで始め、仕上げに前持ちへ。肘から動かし、手首は補助に留めるとムラが減ります。
道具の整備と替え時
芯先は円錐とナイフエッジを使い分けます。広い面は円錐、硬いエッジはナイフ。芯が短くなり角が立たないと境界が鈍ります。紙粉が増えたら軽く払ってから層を重ねます。練り消しは汚れた面を内側に折り込み、清潔な面で光を拾います。
- ベンチマーク早見
- HBで七割を作り、2Bで二割、4Bで一割が目安。最暗部だけ6Bを一点だけ。
- 許容範囲
- 紙目は近距離で粒が見え、離れると均一に見える程度。ムラは一辺三センチ以内。
- 再評価
- 層を二層増やしたら、光源図を再確認。最暗部の位置が動いていないかを確認します。
紙と芯の相性を前提に、筆圧を二種類で使い分けると層の密度が整います。替え時の判断が仕上げの精度を左右します。
構図と投影のデザインで説得力を上げる
影はただ落ちるのではなく、構図に参加します。投影の角度と長さ、形の切れ方を計画すると、視線誘導と奥行きが強化されます。床面の材質で影の見えを調整します。
投影の角度と長さ
光源の高さが低いほど投影は長くなります。構図の対角線に沿わせると視線が流れます。投影の先端を画面外へ逃がすと広がりが出て、大きな面の切れ目に入れるとリズムが生まれます。角度は主要形の長手と少しずらして重なりを避けます。
床面の材質と影
木の床は筋の方向で影が揺れて見え、コンクリートは均一に落ちます。布の上では境界が柔らかく広くなります。水面では明暗が反転するため、反射を別レイヤで考えます。床が明るいと反射光が強まり、形が浮きます。床が暗いと影が沈みます。
切り取りと視線誘導
影の先端を重要なディテールに接続させると、視線が自然に導かれます。影で三角やアーチの形を作ると、画面に安定感が出ます。ハイライトと最暗部を離して配置し、明暗の緊張で中心を作ります。余白は大胆に取り、影でテンポを付けます。
失敗例:投影が主形を分断し、形が読みにくくなる。
回避策:投影は主形のリズムに沿わせ、分断を避ける角度に調整します。
失敗例:床面の質と影の境界が一致せず違和感が出る。
回避策:床の材質語彙を一語で決め、帯の幅に置き換えます。
失敗例:最暗部が複数あり焦点が散る。
回避策:最暗部は一点だけ。その他は半段上で抑えます。
ミニ用語集:投影=物体が表面に落とす影。核心影=物体内部の最も暗い帯。半影=明暗の遷移帯。境界の硬さ=帯の幅で説明する硬度。反射光=周囲から跳ね返る光。
投影は構図要素です。角度と長さ、床材の設定を前提に、最暗部の一点で焦点を作ると、視線が迷いません。
仕上げの統一とチェックリスト
最後は全体の統一です。局所の密度だけを上げると画面が割れます。距離ごとのコントラスト、材質の語彙、最暗部の一点を見直し、必要な手数だけで締めます。削りと持ち上げを併用します。
段階的な仕上げ手順
一度離れて全体を見ます。最暗部が一点か確認し、反射光の幅を再評価。境界の硬さを材質語彙と照合します。次に細部の線を調子に吸収し、粒状感を整えます。最後にハイライトを拾い、投影の先端を整理します。署名は最暗部から離れた位置に置きます。
最小手数の原則
情報は少ないほど強く伝わります。過剰な段階追加はノイズを増やします。仕上げでは一手ごとに離れて確認し、不要なら戻します。練習では制限時間を設け、手数を減らす訓練をします。必要な手数で最大の効果を狙います。
保存と再現性
用紙は酸性紙を避け、描画面を保護紙で挟みます。工程メモを残し、光源図、段階数、番手の比率を書きます。次回の練習で再現し、差分を最小にします。再現性が上がると、本番の応用が楽になります。
実例:球体練習二十枚で段階数を五から七に増やし、最暗部の一点化で所要時間が三割短縮。
ケース:金属円柱で境界帯を狭め、反射光を細くしたら光沢の立ち上がりが明確に。
- ミニ用語集
- 持続圧=長い圧。瞬間圧=短い圧。層=調子の積層。帯=境界の幅。語彙=材質の言い換え。
仕上げは引き算が主役です。最暗部の一点と境界の語彙を基準に、最小手数で全体を整えると作品が締まります。
まとめ
鉛筆の影は、光源設定、三値の起点、境界の設計、反射光の節度、紙と芯の相性、構図への参加で成立します。各段階を言語化し、再現可能な順序に落とすと、毎回の揺れが縮みます。
最暗部を一点に定め、帯の幅を材質語彙に置き換え、反射光を中間調下限で抑えます。仕上げでは手数を最小化し、必要な情報だけを残します。練習では固定光源で球と立方体を繰り返し、段階を五から七へ増やして密度を整えます。
工程メモと光源図を保存し、次回の検証に回すことで、立体感と質感の精度が安定します。日々の短時間練習でも効果は蓄積し、作品全体の説得力が着実に向上します。